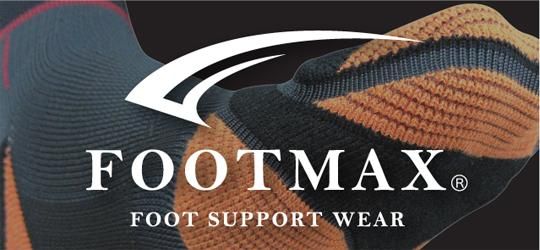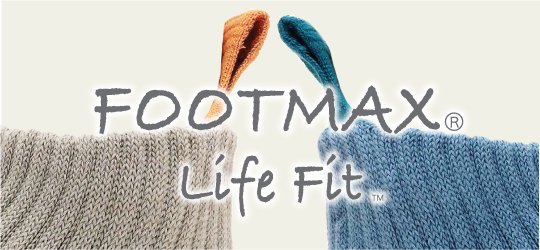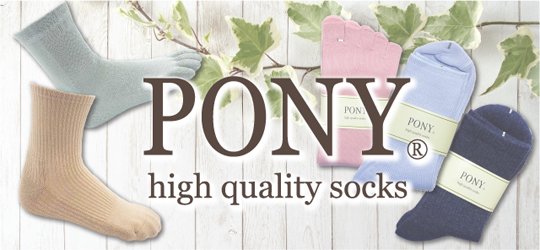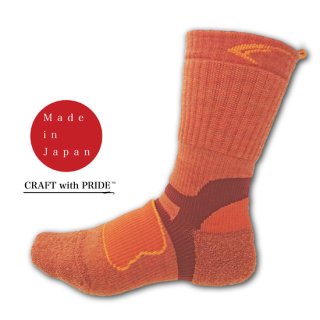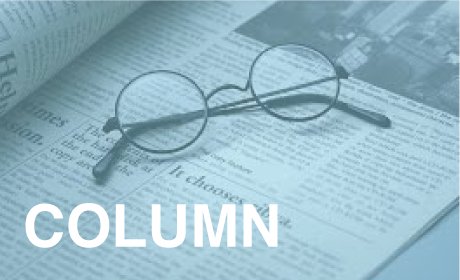マラソンの語源と距離について

2月24日には大阪マラソン開催されます。マラソンといえば一般的に42.195kmのフルマラソンを思い浮かべる人が多いと思います。マラソンという言葉の響きと、なぜそのような中途半端な距離になったのか、今回はそんなマラソンの語源と距離についてのお話しをご紹介してみたいと思います。
マラソンの語源と、フルマラソンの距離42.195kmについて
マラソンの語源は紀元前にギリシャ軍兵士がペルシアの大軍との戦いの勝利を報告するために、マラトンから約40km離れたアテナイまで走ったことに由来しています。勝利の報告後、使命を果たした兵士は力尽きてしまい、この兵士を偲んで、兵士が走った約40kmを第1回オリンピックで走ったのがマラソンの始まりだそうです。当時は大会によって距離が違い、「約40km」という曖昧なルールで実施していました。
では42.195kmという中途半端な距離が採用されたのはいつなのか。それは1908年の第4回ロンドン大会です。当初は42kmで設定していたのですが、このときのイギリス王女アレキサンドラが「スタートは城の窓から見えるように宮殿の庭で、ゴールは競技場にあるボックス席の前に設置してほしい」とリクエストした結果、当初予定していた42kmよりも距離が延び、42.195kmになったと言われています。
このロンドン大会で、最初に競技場に戻ってきたのはイタリアのドランド・ピエトリ選手でした。しかし、彼は競技場の入り口でよろめいてコースを間違え、ついには倒れてしまいます。医師や大会役員に介抱されながらようやくゴールしたものの、助けを借りたことにより、ライバルである他国チームから抗議が入り結果的に失格となります。失格となったものの、ピエトリ選手の頑張りは多くの人に感動を与え、世界的な有名人となります。
1920年(大正9年)、国際競技連盟はマラソンの正式な距離を決める際、このピエトリの悲劇に由来したイギリス陸連からの提案により、第4回ロンドン大会の距離である42.195kmを採用しました。そして、1924年(大正13年)の第8回パリ大会から実施され、今日に至っています。
また、フルマラソン以外にも近年では様々な距離のマラソン競技が広がってきています。
・ウルトラマラソン
42.195km以上の距離を走るマラソンです。50km、70kmなど様々な距離設定がありますが、ウルトラマラソンというと100kmマラソンを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。なかには1550kmという距離のウルトラマラソンもあります。
・ハーフマラソン
フルマラソンの半分の距離の21.0975kmを走ります。フルマラソンに比べてチャレンジしやすい距離ということもあり、市民ランナーに人気の競技です。日本においては秋冬のシーズンには全国で多数の大会が開催されています。
・ハーフ以下のマラソン
10km、5km、1kmなど初心者にもチャレンジしやすい距離で設定されています。フルマラソンやハーフマラソンに向けたトレーニングの一環としても取り組むことができ、ランニングの基礎から始めたい人にも適しています。他にも、決められた距離を既定の人数内で交代しながらリレー形式で走るリレーマラソンや、自己ベスト更新、絶対完走などの目的ではなく、楽しむことを目的としたファンランなど様々なマラソン大会が行われています。